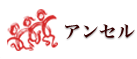アンセル通信

アンセル通信50号を記念してvol1〜vol16をオリジナルをスキャンして掲載しました。
アンセル通信
コラム
第12回 (2021.08.13)
『1.生い立ちと体操との出会い』
私は1935年11月13日に生まれました。2歳と3歳上の兄がいました。一日おきに学校に通い、小学校は3年半だけで試験はなく、
14歳まで自分の生活のために外で働いていました。 両親は自給自足 (野菜、肉、卵、牛乳)出来るくらいの程度の農家でした。余った
牛乳は乳製品加工工場へ、豚は食肉処理場に売っていました。 それらの売り上げで生計を立てていました。
コラム
第11回 (2016..6.12)
『体育環境』
昭和21年12月2日、13時に姉和子が15時に私が世田谷区祖師谷で産声を上げた。其の時、父58歳、母39歳であった。
2歳上に兄がいた。
父喜久雄の出生地は、鳥取県気高郡白兎、因幡の白兎で有名な白兎海岸まで目と鼻の先であった。兄、姉、弟、妹の五人兄弟の真ん中。
年齢にして10歳〜14歳の頃の4年間は毎日往復5里の通学距離を歩いたり走ったりの毎日であった。此の頃すでにベースボールもし、
夏季には海で明け暮れする海の子生活。新鮮な魚と海藻の食生活を送っていた。
コラム
第10回 (2015.9.30)
『マラソン・そして伴走との出会い』
私は寝たきりの義母を2年間看病した経験から(今の様に介護ケアは有りませんでした)、自分のこれからの健康に強く感じ入り━いつでも
どこでも相手がいなくても出来る━マラソンを始めました。50歳過ぎの遅いスタートで、電信柱一本ずつ距離を伸ばすような努力をしましたし
、市川マラソンクラブに入り走り方も習いました。ちょうどマラソンブームの起きた頃で、あちこちの第1回大会に参加しました。3,4年後に
はホノルルマラソンにも挑戦しました。私の走りを見て夫も奮起、夫婦で長野オリンピックのトーチマラソンも走りました。
コラム
第9回 (2015.09.15)
その時私は山口県防府市の海軍兵学校防府分校の校庭に整列していた。昭和20年8月15日炎天下の正午であった。
嘗てない天皇陛下じきじきの放送があるというので、緊張していた。しかし拡声機から聞こえるお声は雑音がひどく、
ほとんど聞き取ること能わず、内容のわからぬまま終了してしまった。一緒に拝聴していた教官や同僚と確かめ合ったが
分からない。多分ソ連への宣戦布告と国民への激励ではないかとの推察もあった。午後の授業が進んでいくうちに
、教官が悲痛な趣で「日本は負けたんだ」と正確な情報を伝えた。これが終戦の「玉音放送」であった。
コラム
第8回 (2015.01.29)
『文部科学大臣賞を受賞して』
2014年9月25日、盛岡市アイスアリーナにて全国スポーツ推進委員研究協議会「岩手大会」が開催され、
その席上栄えある文部科学大臣賞を受賞する事が出来ました。
これもひとえに、多くの諸先輩、スポーツ推進課、事務局の皆様、そしてスポーツ推進委員の皆様方にご指導を頂き、
そして支えて頂いたおかげだと思って居ります。ここに深く感謝し、お礼を申し上げます。
第7回 (2012.03.07)
『海軍兵学校第78期生とデンマーク体操』
帝国海軍兵学校78期生は、昭和20年(終戦の年)の4月3日に入校した兵学校最後の生徒である。15歳前後の少年4000人が入校したが、
それは海軍兵学校の歴史上最大の人数であった。しかし、この時の応募者数は73000人であったというから、まさに精鋭である。そして彼等は
これまで兵学校の置かれていた江田島ではなく、佐世保軍港の東南にある針尾島(東西4km南北8kmの島、現在ハウステンボスの所在地)
において教育・訓練を受けた。
第6回 (2009.01.06)
〔5 ランド・ステウネ(LANDSSTAEVNE)〕
ランド・ステウネは、記録によれば第1回大会は1862年コペンハーゲンで行われ、参加人員は103名とのこと、私が参加したのは
第12回大会で、この時はたまたま7年に1回の年だった。1954年7月22日から25日までの4日間で、場所はオーデンセ。参加人員は
13,000人だった。1990年までは開催を何年に1回するか決まっていなかったが、90年から4年に1回となった。
〔6 留学への感謝〕
ランド・ステウネに出場するための練習期間、更には本番を通して体操の楽しさ、奥の深さ、芸術性と実に多くの事を学び体験する
事が出来たのは、実に幸であった。この大会が終わった後はもとの労働の生活に戻った。時々ある大会にゲストチームとして発表し
たり、講習に同行したり、それなりに忙しかった。今思えば校長が私をいろいろの所に連れて行ってくれたのは、少しでもデンマー
クを知ってもらおうという親切心と、自分の学校に遥か彼方の東洋から勉強に来たという、多少の自慢があったのではないかと内心
思っている。
第5回 (2008.12.10)
〔3 オレロップ国民高等体操学校の授業〕
第1年目に私が受けた授業の大体のカリキュラムは、次のとおりである。
午前中の授業は、(1)全員で受ける音楽と生理学、(2)体操の指導法、(3)インターナショナルだけの生理学、
(4)デンマーク語を習う時間等である。
午後は専ら実技で、体操、水泳、ボールプレーの3科目で毎日あった。
〔4 学校での労働〕
私が留学したのは戦後8年目で、今と違って外資の持出しが大変厳しい時だった。学校の方から送ってもらった費用以外は、
1弗も持出しが出来なかった。私は正味1年9か月滞在したが、費用を払ったのは最初の5か月分だけで、あとは日本を立つ前に
校長に連絡をとって、残りの期間は学校で働く事にして頂いた。
第4回 (2008.09.20)
〔1 旅立ち〕
1931(昭和6)年にシベリヤ経由で来日したニルス・ブックの体操チーム(ブックを始めとして 演技者 男女各12名ずつを含む
総勢28名)は、日本の多くの場所で、デモンストレーションを行った。その一つが当時目白にあった自由学園での発表会だった。
私の家が学園のすぐそばだったので、親に連れられて見学したと思うのだが、まだ4歳であったので当時の記憶は定かではない。
それがデンマーク体操に接した最初であろう。
〔2デンマーク留学での学校生活〕
当時学校は11月3日に始まり、翌年の3月30日までの冬期5か月のコースと、5月3日から7月30日までの夏期3か月のコースの二つだけ
だった。冬期は大部分が男子の学生で、女子は20数名程度だった。夏期は全部女子のみのコース。男子は農家の青年が多かったため、
夏は農繁期でとても忙しい時なので参加出来なかった。共に、年齢は18歳以上と決まっていた。
第3回 (2007.11.11)
『デンマーク体操交歓会の歴史』
デンマーク体操交歓会は、1974年(昭和49年)に第1回を開催してから、本年(2007年)の開催をもって、34回を数えます。
長く続けて来たこの体操交歓会には、私は、次のような経緯の中でその開催に対する思いがあります。
『東山魁夷画伯とデンマーク体操』
1979年(昭和54年)7月15日(日)付の日本経済新聞に、東山魁夷画伯の「朝の体操」という随筆が掲載されました。
「私の一日は、若い時習い覚えたデンマーク体操をすることから始まる」という書き出しで、画伯がデンマーク体操をしていたこと
について書かれていました。
第2回 (2007.10.17)
1950年10月11日、東京YMCAの70周年記念会が共立講堂で行われ、その中にデンマーク体操のデモンストレーションが
ありました。初めて見たこの体操が何か心に残りました。
当時は体が弱く、給料分働いていない気持ちがあったので、YMCAに入会を決意し、健康診断を受けて1951年4月、
23歳で入会しました。
第1回 (1999.0408)
熱中のあまり、我を忘れることは生活の中によくある現象である。
スポーツもその一つである。
身体活動を通して無我夢中になる。或は無我夢中になれるところはたしかにスポーツの特徴であり価値でもある。...
コラムバックナンバー
- 第8回 『文部科学大臣賞を受賞して』 (幹 光子)
- 第7回 『海軍兵学校第78期生とデンマーク体操』 (菊池 昭一郎)
- 第6回 『私の愛するデンマーク体操への旅路』 (羽仁 淳)
〔5 ランド・ステウネ(LANDSSTAEVNE) 6 留学への感謝〕 - 第5回 『私の愛するデンマーク体操への旅路』 (羽仁 淳)
〔3 オレロップ国民高等体操学校の授業 4 学校での労働〕 - 第4回 『私の愛するデンマーク体操への旅路』 (羽仁 淳)
〔1 旅立ち 2デンマーク留学での学校生活〕 - 第3回 『デンマーク体操交歓会の歴史』及び
『東山魁夷画伯とデンマーク体操』 (堀内浩二) - 第2回 『人生を変えた デンマーク体操』 (堀内浩二)
- 第1回 『我を忘れるのがスポーツ、我を思い出すのが体操』 (濱田靖一)